
「私たちが子どもの頃、“遊ぶ”といえば外での鬼ごっこや、お手玉のような手遊びが主流でした。けれど今、孫たちの遊びは画面の中に広がっています。最初は戸惑いや違和感もあったけれど、彼らの世界に少しでも触れてみようと、私はタブレットの電源を入れてみました──それが、思いがけない笑いと絆の時間の始まりでした。」
現代の子育て、そして「孫育て」は、デジタルデバイスと切り離せない時代になりました。スマホやタブレットは、子どもたちの学びや遊びの中に自然と入り込んでいます。しかし、便利な一方で、依存やコミュニケーション不足といった心配もあります。今回は、祖父母としてどのように孫とデジタル機器に向き合えば良いのか、実体験も交えながら考えてみたいと思います。

この子、ばあばに似てない?
と言いながら、孫が見せてきたのは大きなメガネをかけた猫の動画。私は

えー!そんなに太ってないよ~
と笑いながら応じました。二人のやり取りは終始ゆるやかで、でも確実に心の距離を近づけていく。笑った後、孫がぽつりと

ばあばと観ると、もっとおもしろく感じる
と言ったとき、私はこのデジタル時間の温かさを初めて本当の意味で受け入れた気がしました。
変わる「遊び」と「学び」のかたち

昔は外遊びや折り紙、将棋などが中心でしたが、今やタブレットでパズルや知育アプリを楽しむ時代になっています。特にコロナ禍以降、家庭内でできる遊びとしてデジタルコンテンツの活用が進みました。
私の体験談: 小学校1年生の孫が、「おばあちゃん、今日はタブレットでお料理ゲームしよ!」と嬉しそうに話しかけてきた日。最初は戸惑いましたが、一緒に遊んでみると、実はそのゲームが料理の手順や食材の名前を学べる知育アプリだと気づきました。孫は「これはネギ!これはトマト!」と声に出しながら夢中で学んでいました。
スマホ育児のメリットとデメリット

メリット:
- 動画やアプリで知識を楽しく学べる
- 離れていてもビデオ通話でコミュニケーションが取れる
- ゲーム感覚で学べる知育コンテンツが豊富
デメリット:
- 長時間の使用による視力・姿勢の悪化
- スクリーンに没頭しすぎて、家族との会話が減少
- コンテンツの質にばらつきがあり、情報過多になることも
ポイントは「バランス」です。便利さを生かしつつ、リアルな体験や人との触れ合いも大切にすることが求められます。
祖父母だからこそできる「見守り」
私たち祖父母世代には、「デジタル=苦手」という思い込みがあるかもしれません。ですが、孫たちは機械を恐れず、直感的に使いこなしています。だからこそ、私たちは「禁止」ではなく「ともに学ぶ」スタンス共に学でよりそいたいのです。
体験談: ある日、孫が見ているアニメ動画に「これはちょっと内容が怖すぎるのでは?」と不安になりました。そこで、「ねえ、今日はおばあちゃんのおすすめアニメ見てみない?」と昭和の名作アニメを一緒に観る時間を作ったところ、意外にも「面白い!」と喜んでくれました。それ以来、「今日はおばあちゃんセレクトの日」と称して一緒に番組を選ぶ習慣ができました。
時間とコンテンツの「ルール作り」

スマホやタブレットの使用に「時間制限」を設けるのは、目や脳の負担を減らすうえでも重要です。
おすすめのルール例:
- 1回につき30分、1日2回まで
- 食事中やお風呂の前は使わない
- 見るものはあらかじめ一緒に決めておく
祖父母としての視点で、「約束を守る」大切さを伝えられるのも強みです。
アナログとデジタルの“いいとこ取り”
デジタル機器に偏りすぎないように、昔ながらの遊びや体験も意識的に取り入れていくことが大切です。例えば、アプリで描いた絵をプリントして一緒に色を塗ったり、タブレットで見た料理を実際に作ってみる、といった工夫も効果的です。

体験談: 孫がタブレットで見つけた「カレーうどんの作り方動画」を一緒に観て、「じゃあ今度一緒に作ってみようか」と提案。買い物から調理まで一緒に体験したことで、「デジタル情報をリアルに活かす」流れができました。食べながら孫が「これ、自分で作ったやつだよ!」と得意そうに話してくれた笑顔が忘れられません。
おわりに:心をつなぐためのデジタル活用

デジタル時代の孫育ては、「便利」だからこそ、その使い方に”心”が問われます。スマホやタブレットを通じて一緒に笑い、学び、体験を深めることで、世代を超えた絆がより強くなります。
ふとした沈黙の中で、祖父母は孫のあたたかな体温を感じ、孫はふたりのゆったりとした呼吸を感じていました。言葉にしなくても伝わる安心感──それが、家族という“場”の力なのだろうと思います。こうした時間を積み重ねていくことが、子どもの心に残る『大丈夫』の感覚を育んでいくのかもしれません。
これからの孫育ては、“教える”ことより“寄り添う”ことが鍵になるのでしょう。技術に頼ることは決して悪いことではなく、むしろそれを通して心を通わせる術を、私たちはようやく手にしています。大切なのは、画面の向こうではなく、画面のこちら側で笑い合える関係──それを、これからも大事に育てていきたいとおもいます。
祖父母だからこそできる「やさしい見守り」と「丁寧な寄り添い」を、デジタルの力とともに。そんな孫育てが、これからの時代にふさわしい「温もりある育み」なのではないでしょうか
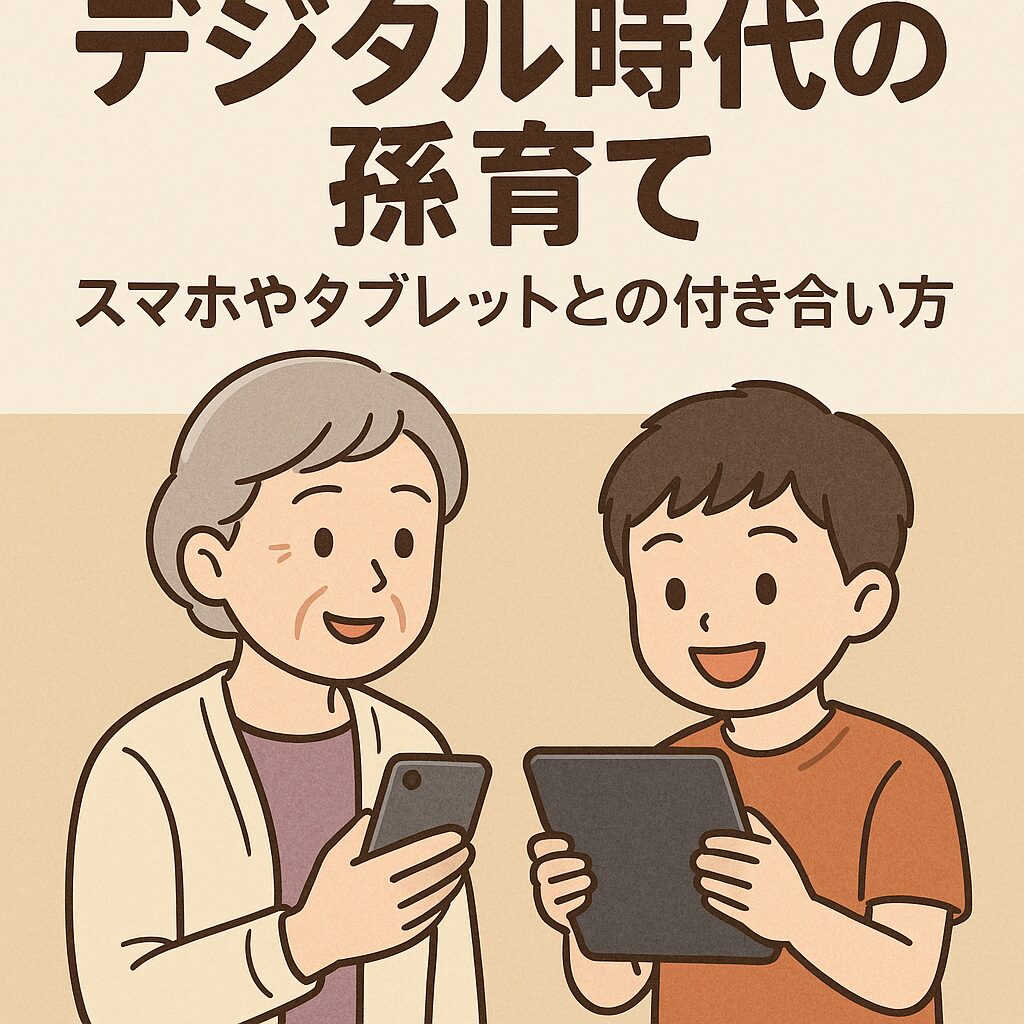


コメント