
「最近、孫との会話がすれ違っている気がする」「もっと心を通わせたい」――そんな思いを抱える方も多いのではないでしょうか。忙しい日々の中でも、ほんの少しの工夫で孫との会話はグッと深まります。
本記事では、会話を広げるための“聞き方”に焦点を当て、聞き上手になるための実践的なヒントを紹介します。家族の絆を育みながら、世代を超えた温かい関係性を築きましょう。
「質問」ではなく「興味」を持って聴く

孫に「学校どうだった?」と聞いても、「別に」「ふつう」という返事しか返ってこないこと、ありませんか?それは“質問”が目的化してしまっているからかも!
ポイントは、相手の言葉に本気で興味を持って耳を傾けること。質問をするという行為そのものよりも、「その子の世界に入りたい」という気持ちが伝わることで、孫の反応は変わります。
たとえば、
- 「最近いちばん笑ったことって何かなあ?」
- 「休み時間って、誰と何してるの?」
など、会話の入り口を「広げる質問」で始めるのがコツです。孫が好きなこと、興味を持っていることに関する会話を心がけると、自分の世界を話しやすく感じてくれるようになります。
孫との会話を深めるうえで、言葉のやりとりだけでなく、「間」や「沈黙」も大切な要素です。大人はつい、何か話さなければと焦ってしまいがち、子どもは黙ったままで考えたり、安心したりしています。 たとえば、孫が何かを話し終えたあと、すぐに返事をせず、少し間を置いて「ふ~ん、そうなんだね」とゆっくり返すだけで、孫は「ちゃんと聞いてくれている」と感じるものです。
また、孫が話したがらないときは、無理に聞き出そうとせず、そっと隣に座って一緒に折り紙を折ったりするだけでも、心の距離は縮まります。言葉がなくても「一緒にいる時間」が、孫にとっては安心の証なのです。
相づちの「種類」を増やす

「へえ」「そうなんだ」だけでは会話が単調になります。表情と声のトーン、言葉のバリエーションを意識すると、孫は“受け入れられている”と感じやすくなります。
- たとえば、「わあ、それは楽しそう!みたかったわ~」「そんなことがあったの?すごいやん、それはびっくりだね~」「ばあばもむか~し、似たようなことあったなあ」
といった感情のこもった相づち+エピソードがポイントです。孫との会話に“思い出の共有”が加わると、距離感がグッと縮まります。
また、ときには沈黙も味方にしましょう。話が止まったときに無理に埋めようとするのではなく、笑顔で「待つ」姿勢も、安心感につながります。
孫の話に対して、「それはすごいね」「うれしかったんだね」「悔しかったんだね」といった共感のひとことを添えるだけで、会話はぐっと深まります。 大切なのは、評価やアドバイスではなく、まずは気持ちに寄り添うこと。たとえば、孫が「今日、友だちとケンカしちゃった」と話したとき、「どうしてケンカしたの?」と原因を探る前に、「そうだったんだね、つらかったね」と気持ちを受け止めることで、孫は安心して心を開いてくれます。
先日もお友達と思い違いでけんかになった7歳の孫のき~ちゃんが、もうひとりのお友達が誤解をといてくれて、仲直りできたんだ~と話してくれました、子供でも思いがけないけんかはつらかったようで、仲直りできてホッとしました。
「昔話」は時代をつなぐ架け橋に

「私たちの時代はこうだったのよ」と話すとき、その背景にある価値観を押しつけるのではなく、「あなたならどう感じる?」と問いかけると対話が深まります。
たとえば、 >「おばあちゃんの時代は、学校から帰ったらランドセルを玄関に放り投げて、すぐに外へ走ってたの。でも今は宿題の量も違うし、遊ぶ場所も少ないよね」
というように、共感と時代比較を添えると、孫も「自分の話をしていいんだ」と感じやすくなります。
「話をさえぎらない」+「沈黙を受け入れる」
話の途中で口を挟むクセがある人は、無意識のうちに会話をコントロールしがち。これは孫にとっては「話すのをやめようかな」というサインになります。
職場でもこういう人いますが、自分も気をつけなくちゃ!
特に思春期にさしかかると、孫は自分の考えを整理しながら話そうとします。そこに大人の言葉でかぶせてしまうと、「伝わらない」という印象を持たれがちです。
「聴く」時間を尊重し、合いの手ではなく“うなずき”で応える。沈黙の数秒が、安心と信頼につながります。
孫の「マイブーム」に寄り添う
ポケモン、YouTube、推し活、最新アプリ…大人から見るとなんだかよくわかりません。
よくわからない世界でも、孫にとっては「毎日を彩る大切なもの」。その存在に敬意を持って接すると、驚くほど話は弾みます。
たとえば、
- 「今一番好きなユーチューバーは誰?」
- 「それってどんなところが面白いの?」
と“肯定ベース”で尋ねることが大切です。知らなくて当たり前。でも、知ろうとする姿勢が、孫にはうれしく映ります。
私は毎日2歳と7歳のまごとユウチュウブを見ていますがていますが、中々おぼえられないので、何度も聞きながら教えてもらいます。
「聞く」ことは「信じる」こと
孫の話を聞くということは、その子の世界を信じることでもあります。たとえ大人から見て些細なことでも、孫にとっては大きな出来事。 「そんなことで泣かないの」「それは違うよ」と否定せず、「そう感じたんだね」「嫌だったんね」と受け止める姿勢が、孫の子持ちを尊重してあげるようにします。
共に体験する=会話が生まれる瞬間を増やす

言葉だけでは届きづらい想いや考えも、「一緒に何かをする」ことで自然とこぼれ出ます。
おすすめは、
- 一緒に季節の料理をつくる
- 図書館や近所の公園に出かける
- 折り紙や工作をしながら思い出話をする
こうした体験を通じて交わす言葉は、孫の心に残りやすく、何気ない時間が“思い出”へと変化していきます。
まとめ:聞き上手が育てる“世代を超えた信頼”

孫との会話で大切なのは「何を言うか」より「どう聴くか」。ほんの少しの意識で、孫の声には深みと表情が生まれます。
-
興味を持って聴く、共感を添える、時代をつなぐ視点を持つ、沈黙も受け入れる、一緒に体験する
この5つのヒントがあれば、孫との会話は、ただの言葉のやりとりから、心のつながりへと進化していきます。
今日のひとことが、明日の信頼になりますように。子どもたちが「話したくなるばあば」を目指して、まずは聴くことから始めてみましょう。
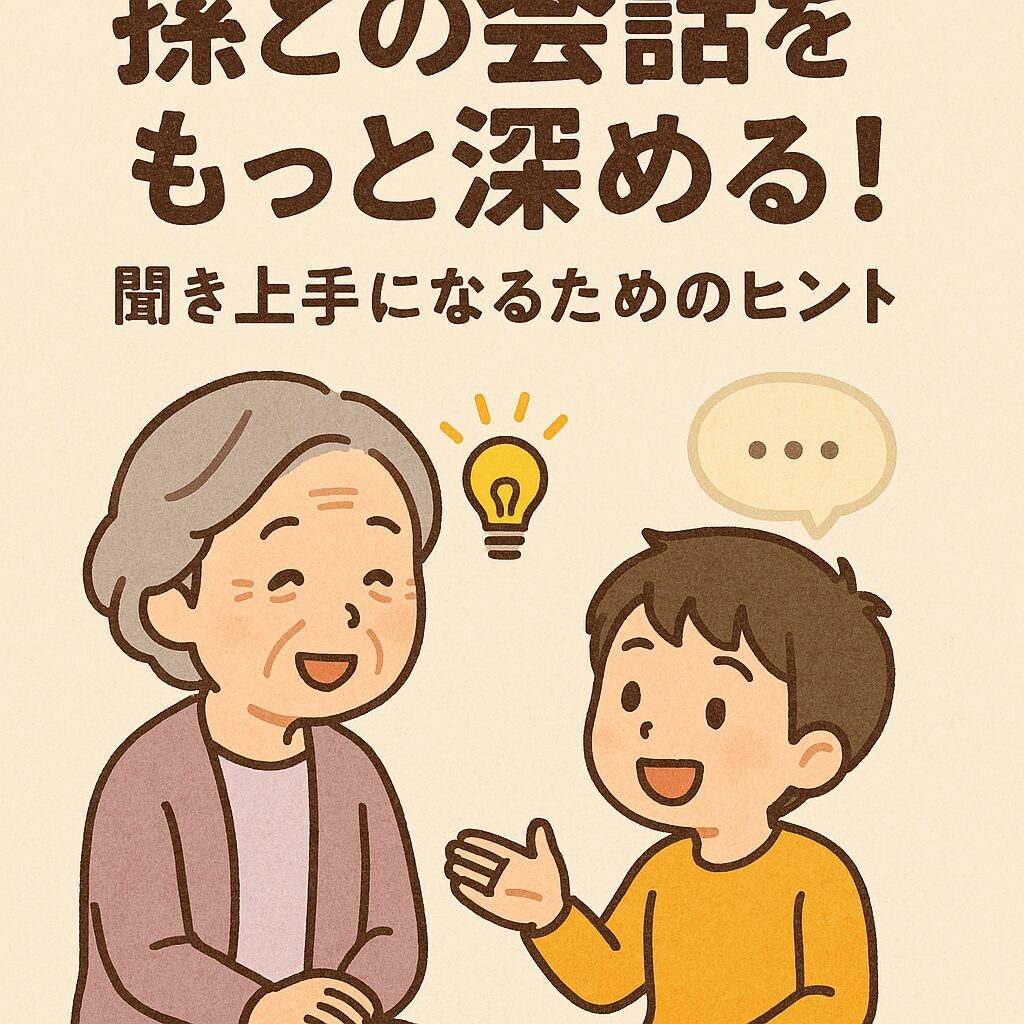


コメント