おもちゃは、ただの遊び道具ではありません。 それは、子どもたちの成長を支え、家族の絆を深める“心のツール”です。

私には1歳・2歳・7歳の三人の孫がいます。彼らと過ごす日々の中で、おもちゃがどれほど大切な役割を果たしているかを、何度も実感してきました。 この記事では、祖母としての実体験を交えながら、年齢ごとのおすすめおもちゃ、そしてサブスクサービスの活用法について詳しくご紹介します。
1歳・2歳の孫におすすめの遊び道具
キーワード:安全性・五感刺激・手指の発達

この時期の子どもは、見る・触れる・聞くといった感覚を通して世界を探検しています。 我が家で特に人気なのは、木製のカラフルなブロック。穴に通したり積み上げたりすることで、集中力や手先の器用さが自然に育まれます。
また、音の出る楽器セットも大活躍。マラカスやタンバリンを振ったり叩いたりすることで、音の変化に興味を持ち、指先の力加減を学んでいきます。
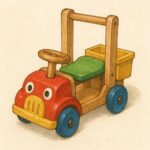
押し車は、室内での冒険にぴったり。転んでもすぐに立ち上がる姿に、遊びが「挑戦する力」を育ててくれていることを感じます。
エピソード:音で始まる家族の朝
 1歳の孫に贈った「ばあば手作りの楽器セット」。最初はマラカスを振るだけでしたが、次第にリズムを感じて踊り出すように。 家族みんなで手拍子をしながら、朝の音遊びが我が家の定番になりました。 鈴やカスタネットを加えると、音の違いに気づき、孫の表情がどんどん豊かになっていくのが分かります。
1歳の孫に贈った「ばあば手作りの楽器セット」。最初はマラカスを振るだけでしたが、次第にリズムを感じて踊り出すように。 家族みんなで手拍子をしながら、朝の音遊びが我が家の定番になりました。 鈴やカスタネットを加えると、音の違いに気づき、孫の表情がどんどん豊かになっていくのが分かります。
2歳〜3歳の孫にぴったりの遊び道具
キーワード:模倣・創造・社会性の芽生え
2歳を過ぎると、子どもは「まねっこ」や「ごっこ遊び」に夢中になります。 ままごとセットに空き箱やシールを加えて、即席のお店屋さんを開店!家族が交代でお客さん役をすると、順番を守ることや会話のキャッチボールが自然に身につきます。
積み木遊びでは、色を揃えたり高く積んだりと、ルールを作って遊ぶことで集中力と創造力が育まれます。 完成した作品を写真に撮って「作品展」を開くと、孫の誇らしげな笑顔が見られます。
エピソード:小さな店員さんの大活躍

2歳の孫に贈ったアンパンマンのままごとセット。 「いらっしゃいませ〜」「おいしいですよ〜」と、まるで本物の店員さんのように振る舞う姿に驚きました。 遊びの中で言葉のやりとりが増え、社会性が育っているのを実感。 積み木では「もっと高く!」「赤いのだけで!」と、自分なりのルールを作って遊ぶようになり、集中力がぐんと伸びました。
7歳の孫におすすめの知育玩具
キーワード:論理的思考・創造力・挑戦心

小学生になると、遊びの内容がより複雑になり、「考える」「作る」ことに興味を持ち始めます。 この時期におすすめなのは、プログラミングトイ、ボードゲーム、クラフトキットなど、思考力と創造力を刺激するアイテムです。
| ランキング | 商品名 | 育まれる力 |
|---|---|---|
| 1位 | ネフスピール | 空間認識・造形力 |
| 2位 | キュボロ スタンダード32 | 論理的思考・集中力 |
| 3位 | トーマス レッツゴー大冒険 | 手先の器用さ・探究心 |
| 4位 | ジスター 天才のはじまり | 紐通し・創造力 |
| 5位 | アクアレルム ジュニア | 色彩感覚・表現力 |
| 6位 | マグネット3D立体パズル | 空間認識・構成力 |
| 7位 | くもんのジグソーパズル | 集中力・達成感 |
| 8位 | レゴ デュプロ | 自由な発想・論理性 |
| 9位 | 型はめパズル | 形の認識・器用さ |
| 10位 | スマイルサッカー 3号球 | 協調性・運動能力 |
エピソード:工作で育つ自信と誇り
7歳の孫に木製のクラフトキットを贈ったときのこと。 最初は「むずかしい…」と戸惑っていましたが、完成すると「見て!ぼくが作ったよ!」と満面の笑み。 その後、図工の授業でも積極的に手を挙げるようになり、「作ること」が自己肯定感につながることを改めて感じました。
おもちゃのサブスク活用術
キーワード:成長に合わせた選択・買いすぎ防止・親の安心感
「何を選べばいいのか分からない…」そんな悩みから始めたサブスク。 我が家では「トイサブ!」や「AndTOYBOX」を利用しています。定期的に届く知育玩具に、孫たちは「次は何が来るかな?」と目を輝かせて待っています。
返却のタイミングでは「おもちゃ卒業式」を開催。遊んだ思い出を振り返りながら、成長を記録する時間にしています。
サブスクの最大の魅力は、孫の発達段階に合わせてタイムリーにおもちゃを試せること。 親からも「安心して使える」「収納に困らない」と好評です。
エピソード:迷わないおもちゃ選び
以前は「どんなおもちゃが合うのか分からない…」と悩んでいました。 でもサブスクを使い始めてからは、孫の反応を見ながら選べるように。 「これは好き」「これはすぐ飽きた」など、遊びの傾向が見えてきて、無駄な買い物が減りました。 結果的に、孫にぴったりのおもちゃを選べるようになり、親子ともに満足度が高まりました。
おもちゃ選びにおすすめのショップ
- ボーネルンド(京都伊勢丹・大阪グランフロント) → 実際に手に取って遊べる体験型ショップ。スタッフのアドバイスも丁寧で安心。
- トイザらス(精華町近郊なら奈良店) → 年齢別に豊富なラインナップが揃っていて、兄弟それぞれに合ったおもちゃが見つかります
まとめ:おもちゃは家族の物語を紡ぐ道具
おもちゃ選びは、孫との時間を豊かにする第一歩。 年齢や性格に合わせたアイテムを通じて、家族みんなで「学び」と「感動」に満ちた毎日を過ごしています。
私自身、祖母としての視点から「どんな遊びが今の孫に必要か」「どんな体験が心に残るか」を考えるようになりました。 そして気づいたのは、おもちゃは単なる道具ではなく、“家族のストーリーを紡ぐきっかけ”だということ。
たとえば、1歳の孫がマラカスを振って笑った瞬間。 2歳の孫が「いらっしゃいませ!」と元気に声を出した瞬間。 7歳の孫が「私が作ったよ!」と誇らしげに作品を見せた瞬間。
それぞれの瞬間が、家族の記憶に刻まれ、未来への自信につながっていくのです。
祖母だからこそ伝えられる「遊びの力」
子育てを終えた世代だからこそ、見えるものがあります。 それは、「遊びの中にある育ちの芽」。
親世代が忙しくて見逃しがちな小さな成長も、祖母の目にはしっかり映ります。 「今日は少し長く集中してたな」「昨日より手先が器用になってる」 そんな気づきが、次のおもちゃ選びのヒントになります。
また、祖母が選ぶおもちゃには“思い出”が宿ります。 自分の子育て時代に使っていたもの、昔ながらの遊び道具、そして今の時代に合わせた知育玩具。 それらを組み合わせることで、孫にとって「新しいけれど懐かしい」体験が生まれます。
おもちゃ選びのコツ:祖母目線でチェックしたいポイント
最後に、私が実際におもちゃを選ぶときに意識しているポイントをまとめてみました。
- ✅ 孫の「今の興味」に合っているか
- ✅ 安全性(素材・角の処理・誤飲の危険)
- ✅ 成長段階に合わせた難易度
- ✅ 家族みんなで遊べるかどうか
- ✅ 長く使える工夫があるか(組み替え・発展性)
- ✅ 親世代にも好評かどうか(収納・衛生面)
このチェックリストを使うことで、買いすぎや失敗を防ぎつつ、孫にぴったりの一品を選ぶことができます。
おもちゃと一緒に育つ「家族のアルバム」
私は、おもちゃで遊ぶ孫の姿を写真に残すようにしています。 それは単なる記録ではなく、「成長の証」として家族みんなで振り返る宝物になります。
たとえば、初めて積み木を積んだ日。 初めて「ばあば、見て!」と声をかけてくれた日。 その瞬間を写真に残し、コメントを添えてアルバムにまとめると、孫自身も「私、こんなことできたんだ!」と自信につながります。
サブスクのおもちゃ返却時にも、「卒業証書」を作って渡すと、遊びが“思い出”に変わります。 こうした工夫が、家族の絆をより深く、温かくしてくれるのです。
これからのおもちゃ選びに向けて
おもちゃ選びは、孫の成長を支えるだけでなく、祖父母としての喜びや発見にもつながります。 「こんな遊び方があるんだ」「こんなに集中できるんだ」 そんな驚きが、毎日の暮らしに彩りを添えてくれます。
これからも、孫の年齢や興味に合わせて、柔軟に選び方を工夫していきたいと思います。 そしてこのブログでは、祖母だからこそ気づけた「遊びの力」や「家族のつながり」を、惜しみなく発信していきます。
おわりに:おもちゃは“愛のかたち”
おもちゃは、孫への愛情を形にする手段。 それは、言葉では伝えきれない「想い」を、遊びを通じて届ける方法でもあります。
孫が笑うと、家族が笑う。 孫が挑戦すると、家族が応援する。 そんな循環が、家庭の中に小さな奇跡を生み出してくれます。
これからも、孫たちの「今」を大切にしながら、心を込めておもちゃを選び続けたいと思います。 そしてその選び方や体験を、同じように悩み、喜びを分かち合いたい祖父母の皆さんへ、丁寧に届けていきます。
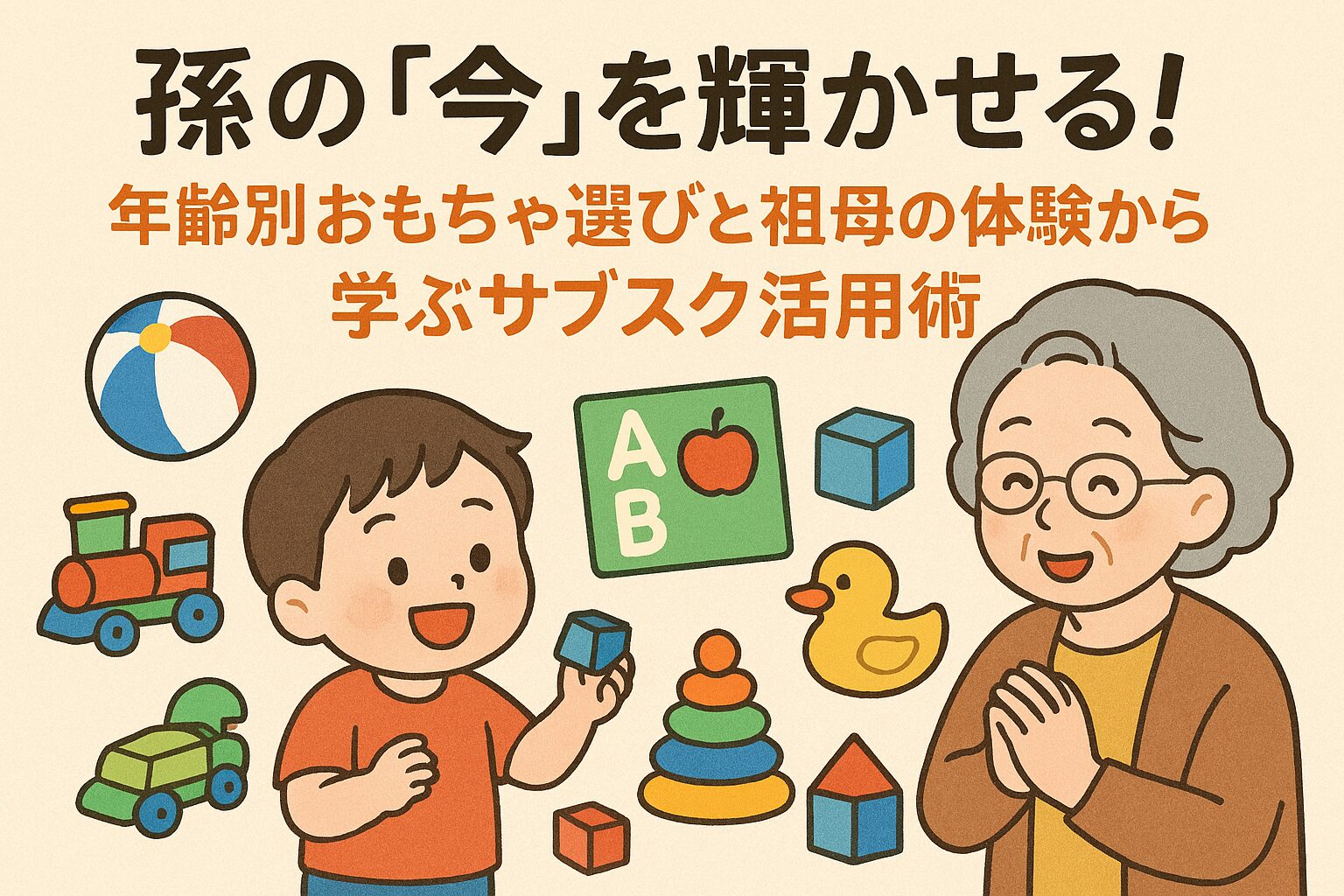


コメント